パリ協定、カーボンニュートラル、ゼロエミッション、ガソリン車販売禁止からの、電気自動車(EV)へEUと中国を中心にシフトしている自動車業界。単なる環境問題だけではなく、各国経済の思惑うごめくEVですが、今回は、これからEVを所有してみたいEV初心者に向けて、EVの最適な充電方法について、お話していこうと思います。
日産リーフをはじめ、三菱i-MiEV、ホンダe、テスラなど、徐々に増え始めたEVは、さまざまな意見がありますが、今後重要となってくるモビリティのひとつだということは間違いありません。
 世界中でEV量販に成功した功労者が日産リーフだ。累計生産台数は50万台を突破した
世界中でEV量販に成功した功労者が日産リーフだ。累計生産台数は50万台を突破した筆者は、過去に一年ほど、日産リーフをマイカーとして所有していました。EVならではの魅力も、EV乗りでないと分からない苦労も、身をもって体感しています。
■「自宅に充電設備」が一番理想
充電方法には、「普通充電」と「急速充電」の2通りがあります。最近は、EVが充電しているところを見かけることも多くなりましたが、自動車ディーラーや高速道路のサービスエリア、大型スーパーの駐車場、コンビニなど、街中に設置されている充電設備は、その多くが「急速充電」用です。
現在日本には、EVやPHEV(プラグイン・ハイブリッド車)用の急速充電設備が、約8000基あります。ガソリンスタンドは約3万箇所(2019年度のデータ、そのうちセルフ式が1万箇所)ですから、まだまだガソリンスタンドの方が多い状況ですが、減り続けるガソリンスタンドの数に対し、急速充電設備は増え続けています。
しかし本来、EVに望ましい充電方法は、急速充電ではなく、普通充電です。なぜなら、急速充電の繰り返しは、駆動用バッテリーへダメージを与え、バッテリーの寿命に影響を及ぼす可能性があるからです。
 本来、EVに望ましい充電方法は、自宅やオフィスの駐車場など、普段、自動車を保管している場所へ充電機を設置し、「普通充電」をするのが良いとされている
本来、EVに望ましい充電方法は、自宅やオフィスの駐車場など、普段、自動車を保管している場所へ充電機を設置し、「普通充電」をするのが良いとされているもっとも望ましいのは、自宅やオフィスの駐車場など、普段、自動車を保管している場所へ充電機を設置し、クルマを使っていない夜間に充電すること。夜間の電気代が安い時間帯に充電する方が、ランニングコストが安くなります。また、EVユーザー同士の「譲り合い」として、街中の充電設備は、緊急の方のために、空けておいたほうがいい、ということもあります。
ただし、自宅に普通充電設備を設置できる方は、戸建て住宅をお持ちの方に限られるでしょう。マンション等の駐車場に、充電設備を導入することは(マンションオーナーがEVへ理解ある方でない限り)ほぼ不可能ですし、共用スペースにある充電器を、長時間占有するのもマナーとしてよろしくありません。そうした場合は、公共の急速充電器にて充電を賄うことになります。
■マンション住まいでも悪くはない
筆者がEVに乗っていた時はマンション住まいでしたので、初めから急速充電のみの利用で過ごしていました。出先から帰る途中、近くのコンビニやディーラーへ立ち寄り、30分時間をつぶしながら急速充電をして帰宅する、という流れです。
出先では極力充電しなくても済むように、残りの航続距離で自宅まで戻ることができるか、いつも考えながら走行していました。このとき、目的の急速充電器が埋まっていた場合を想定し、第2候補を決めておくのがポイント。第1候補が使用中でも、すぐ切り替えて、第2候補へ移動します。
 大容量のEVバッテリーは、ただ走ることに使うだけでなく、家庭への給電や余った電力を蓄えることもできる。このV2H(Vehicle to Home)システムは、停電時にも家中のほとんどの家電に給電が可能となる
大容量のEVバッテリーは、ただ走ることに使うだけでなく、家庭への給電や余った電力を蓄えることもできる。このV2H(Vehicle to Home)システムは、停電時にも家中のほとんどの家電に給電が可能となるもしも、自宅が戸建て住宅で、充電設備が設置できるのであれば、筆者も間違いなく、普通充電器(工賃含めて約10万程度の資金が必要)を導入していたでしょう。夜間、自宅の普通充電器にクルマを接続しておけば、(キムタク出演の日産のCMのように)毎朝、満タン充電でスタートすることができ、よほどの距離を運転しない限り、一日の途中で充電する必要はありません。
クルマによっては、例えばタイマー予約で、暖房をつけた状態でクルマを駐車場で待機させておくなど、便利な機能も使えます。
■テスラの特権、スーパーチャージャーで充電時間は約半分に
テスラ(モデルS、モデルX、モデル3)では、「ウォールコネクター」と呼ばれる自宅用充電器のほか、日本国内に20カ所以上設置されている、「スーパーチャージャー」と呼ばれるテスラ車専用の急速充電器を使用することができます。
 日本国内に20カ所以上設置されているテスラのスーパーチャージャー
日本国内に20カ所以上設置されているテスラのスーパーチャージャー最新のスーパーチャージャー・バージョン3(V3)と呼ぶ超急速充電器であれば、従来の充電時間を約半分程度にまで短縮が可能。加えて、日本各地にある急速充電器「CHAdeMO(チャデモ)」、そして「普通充電器」にも対応しています。
■まとめ
最近はPHEVを見かけることが増えてきました。EV乗りとしては、航続距離がギリギリの状態でサービスエリアに飛び込んで、PHEVが列をなして充電待ちをしているのを見ると、純EVに譲ってほしいと、思ってしまったことがしばしばありました。
ちなみに筆者は、EVを1年間所有したのちに、クリーンディーゼルへとクルマを替えました。純ガソリン車がなくなる前に、現代のディーゼル車の良さを堪能しておきたいと思ったからです。航続距離は大幅に増えて満足していますが、EVのなめらかな操縦フィーリングは、いまでも忘れられません。まだまだ設備が充実しているとはいえない状況ではありますが、一度はEVを体感してみてほしい、と思います。








Text:Kenichi Yoshikawa
Edit:Takashi Ogiyama
Photo:Nissan,Tesla,AC
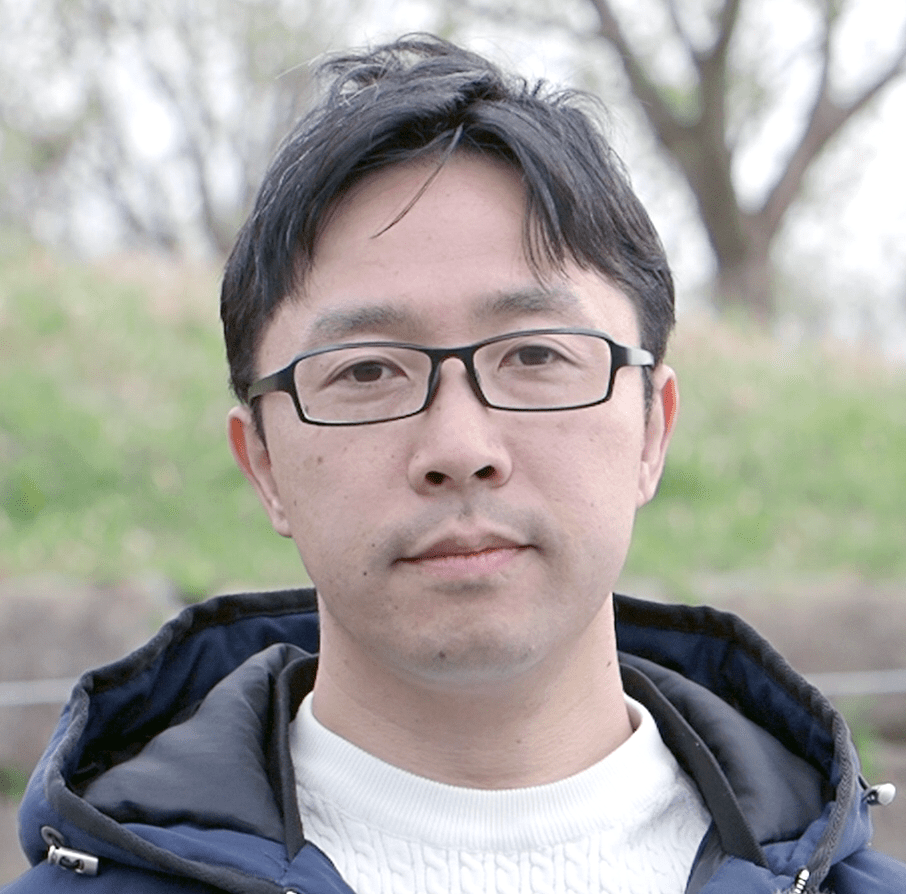 吉川賢一(自動車ジャーナリスト)1979年生まれ。元自動車メーカーの開発エンジニアの経歴を持つ。カーライフの楽しさを広げる発信を心掛けています。
吉川賢一(自動車ジャーナリスト)1979年生まれ。元自動車メーカーの開発エンジニアの経歴を持つ。カーライフの楽しさを広げる発信を心掛けています。












