世界中から圧倒的な支持を集める、トヨタランドクルーザー(以下ランクル)。「ランドクルーザー」という名のクルマが誕生したのは、なんと1954年。70年近くも前のことだ。

ランクルの特徴は何といっても、悪路走破性の高さ。しかし、日本では若干持て余してしまうほど、ボディがデカい。それでもランクルは、確実に売れ続けてきており、現在、日本で新車販売されているトヨタ車で、もっとも長い歴史をもつクルマでもある。

現行型であるランクル200は、既に登場から12年。ここにきて、次期型の姿がリークされ始めた。国内外さまざまなメーカーからいくつものクルマが誕生し、そして消えていくなか、さらにランクルの歴史は続くようだ。
ここまでランクルが支持されるのには、いったいどんな理由があるのだろうか。
■ランクルのメイン市場は「中近東」
まず国内市場で、ランクルがどれほど販売されているのか調べてみた。過去5年間のデータだと、年間1.7万台から2.9万台、月にすると2000台ほどが売れている。この数字だけを見ると、「大したことは無い」と思うかもしれない。だが、ランクルの主戦場は海外市場だ。
 もともとは、警察予備隊(現自衛隊)への納入を目的として開発されたランクル。その座は三菱がライセンス生産していた「ジープ」に譲ったが、その後、現在に至るまで活躍し続けている
もともとは、警察予備隊(現自衛隊)への納入を目的として開発されたランクル。その座は三菱がライセンス生産していた「ジープ」に譲ったが、その後、現在に至るまで活躍し続けている2020年8月、「ランドクルーザー」シリーズのグローバル累計販売台数は、1000万台を突破した。ランクルの原型は、1951年8月に試作車「トヨタジープBJ型」。以来、約170の国や地域で販売されてきた。
 ランドクルーザーの国内登録車台数の過去5年間の推移 年間1.7万台から2.9万台、月に2000台ほどが売れている状況だ
ランドクルーザーの国内登録車台数の過去5年間の推移 年間1.7万台から2.9万台、月に2000台ほどが売れている状況だもともとは警察(軍用)車両として誕生し、北米などで支持を集めたランクルであるが、ランクルがいま狙う市場は、主に中東地域。年間の販売台数約38万台のうち、3割以上となる約13万台が中近東で売れている。中東地域に住む、お金持ちの若者は、週末のたびに砂漠へと出かけ、ランクルや、レクサスLX、ニッサンサファリ、ポルシェカイエン、といったクルマでの乗り比べを楽しむのだそうだ。
 ランクルが最も売れている最大の試乗は中近東。砂漠のようなラフロードを走るクルマとして、信頼性が高い故に大人気だ。(TOYOTA資料)
ランクルが最も売れている最大の試乗は中近東。砂漠のようなラフロードを走るクルマとして、信頼性が高い故に大人気だ。(TOYOTA資料)中東でのランクルは、観光にも重宝している。中東の経済の中心都市、ドバイの観光では、「デザートサファリ」と呼ばれる砂漠ツアーが定番となっている。ドバイを走る幹線道路から少し逸れると、もうそこは砂漠地帯。その砂漠地帯をクルマで豪快に走り回る、というツアーだ。タイヤが砂の中に沈んで走れなくなってしまわないよう、タイヤの空気を抜き、砂丘の山をぐいぐいと、まるでジェットコースターのように走る。それにランクルが、多く使われているのだ。
 砂漠でランクルを豪快に走らせるなんて、なんとも贅沢な遊びだ
砂漠でランクルを豪快に走らせるなんて、なんとも贅沢な遊びだもちろん、こうした使い方だけでなく、その走破力と耐久性を活かし、病院まで数百キロある荒れた道のりを走破して病人やケガ人を輸送したり、災害地へ出向いて救命活動に従事する、といった使われ方もしている。移動できないことで生死に関わる地域にとって、ランクルはまさに「命綱」なのだ。
■「究極の耐久性」はこうして設計されている
このような使われ方をするランクルは、一般的なクルマとは、求められる耐久性のレベルが違う。一般的なクルマでは、例えば、路肩のコンクリートブロックに低速でゴツンと乗り上げてしまっても、サスペンションやタイヤ、ホイールが「壊れない」程度の強度を持つように設計される。が、ランクルなどの大型SUVでは、路肩ブロックの2倍以上の高さに正面から突っ込んで、足回りが壊れずに「乗り越えられる」ように設計される。
 「ランクルなら安心」というユーザーから信頼は、ランクルにとっては大きな財産だ
「ランクルなら安心」というユーザーから信頼は、ランクルにとっては大きな財産ださらには、普通車には絶対にない要件だが、「ビッグジャンプ」がこなせることも重要だという。大きくうねった砂漠の地を走ると、クルマがジャンピングすることは、日常茶飯事だ。車重3トンにもなるクルマがジャンプすることで、その足回りやボディに大きな衝撃を受けても、絶対に壊れないことが求められる。
そのため、ラダーフレーム構造の強固なボディにしたり、サスペンションストロークを大きく確保したり、ショックアブソーバーの容量を大きくしたり、大きくて重たいV8エンジンを支えるエンジンマウントを強化したりと、オフロードを走るレースカー並みに、耐久性の確保が重要になる。

しかも、レーシングカーと違うのは、車内ではエアコンを効かせて、涼しい顔をして、運転を楽しむだけの、快適性も確保しないとならない。
こうした性能の高さが、海外のユーザーから信頼されることにつながっているのだ。
■人気車ゆえのつらさも
ランクルは、旧式であっても、中古車相場の値崩れがしにくい。そのためか、盗難車ランキングでも常にTOP3に入るほど、窃盗にあいやすいクルマだ(車はパーツにバラされて、海外へ輸出されている可能性もある)。

人気車ゆえのつらいところだが、ランクルはそれだけ皆に必要とされるSUVでもある。もし機会があるならば、一度は乗っていただきたい一台だ。
Text:Kenichi Yoshikawa
Photo:TOYOTA
Edit:Takashi Ogiyama
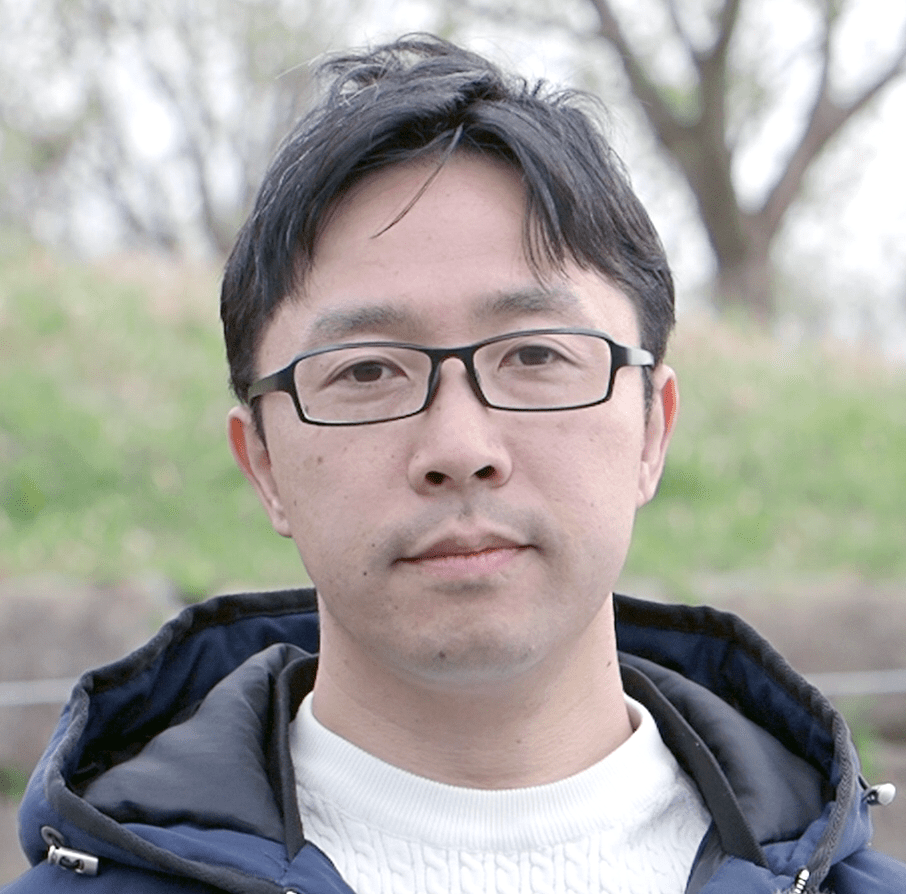 吉川賢一(自動車ジャーナリスト)1979年生まれ。元自動車メーカーの開発エンジニアの経歴を持つ。カーライフの楽しさを広げる発信を心掛けています。
吉川賢一(自動車ジャーナリスト)1979年生まれ。元自動車メーカーの開発エンジニアの経歴を持つ。カーライフの楽しさを広げる発信を心掛けています。











